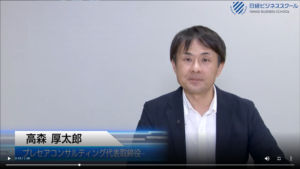中小企業診断士向け理論政策更新研修に登壇しました
弊社代表取締役 高森厚太郎が、中小企業診断士向け理論政策更新研修に登壇しました。
中小企業診断士の資格は5年毎に更新が必要であり、その要件の一つに「理論政策更新研修」の受講があります。高森代表はその理論政策更新研修の講師として2017年から毎年登壇しています。
今回はなんと静岡や大阪と、遠方からご参加の方も。社内診断士の方、独立起業して間もない方から診断士歴20年以上の方まで、14名の方にご参加いただきました。
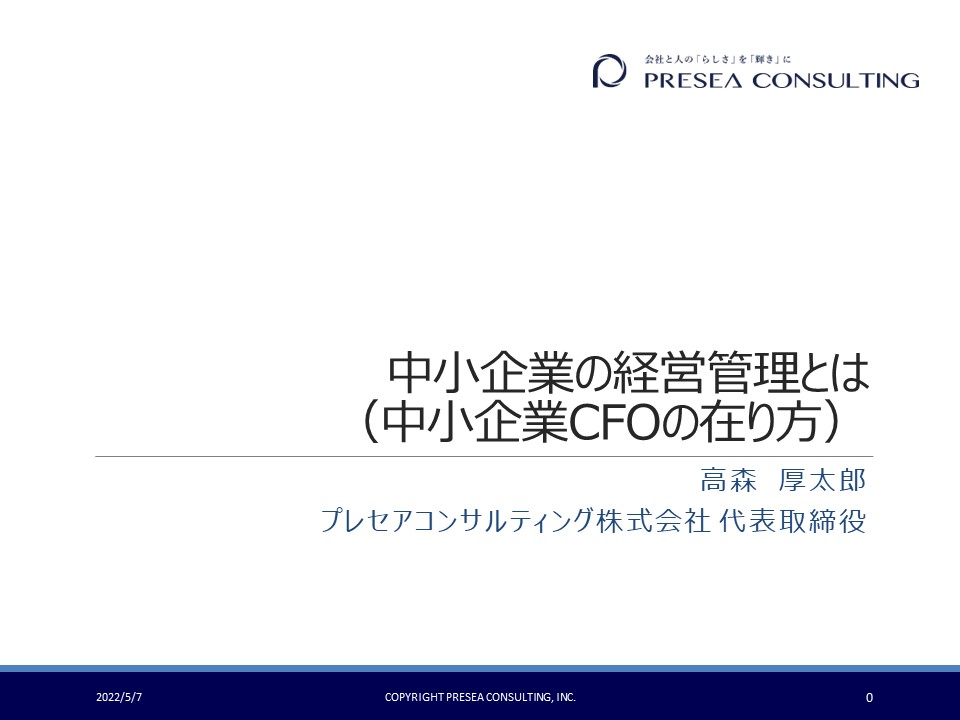
「中小企業の経営管理とは(中小企業CFOの在り方)」のパートでは、診断士を含む士業の経営支援における課題に始まり、中小企業の経営の全体像、中小・ベンチャー企業CFOの在り方を含めて解説しました。
「中小企業の経営管理とは(中小企業CFOの在り方)」のパートでは、診断士を含む士業の経営支援における課題を明らかにし、中小企業の経営の全体像を解説。
続いて中小・ベンチャー企業の社外CFO(パートナーCFO®)の在り方と診断士としての可能性の広がりをお伝えしました。
本研修に参加する診断士の方は次のような課題が挙げられます。
ー(社内診断士なら)本業以外に副業として、中小ベンチャーの支援をすることができる、稼ぐことができる
ー(独立診断士なら)差別化の武器となる、単価を上げられる、新規開拓やイベント・セミナーのネタになるヒントが欲しい
ークライアントの経営上の悩みに応えられる方法を知りたい
今回集まった診断士の方も金融機関出身や事業会社の経理・経営企画担当者が多く、経営者のパートナー足りうる社外CFO(パートナーCFO®)の事例に高い注目が集まりました。
質疑応答では
「CFO8マトリックス®に自分がやりたかったことが整理されている。どうやって自分の専門性を決めていけばよいか」
「CFOと聞いて想像した内容より範囲が広いが、どのレベルまで理解しておく必要があるか」
など、社外CFO(パートナーCFO)としての専門性の作り方に関する質問や、
「公的支援以外で継続支援をする入り口はどうやって作るのか」
「会社の目指す姿は社長といつ、どんな風に共有するものなのか」
「社外CFOとして月2時間の面談以外にどんなことをするのか。書類作成が無尽蔵に増えない工夫は何か」
など、具体的なアプローチ方法やスタンスについてお答えしました。
また、社長がパートナーCFO®とのディスカッションに価値を感じる理由と、パートナーとして社外にいながらコミットメントする姿勢、そして事業や経営者との相性の重要さをお伝えし、参加者それぞれの立場で診断士活動に活かせるヒントをお届けしました。
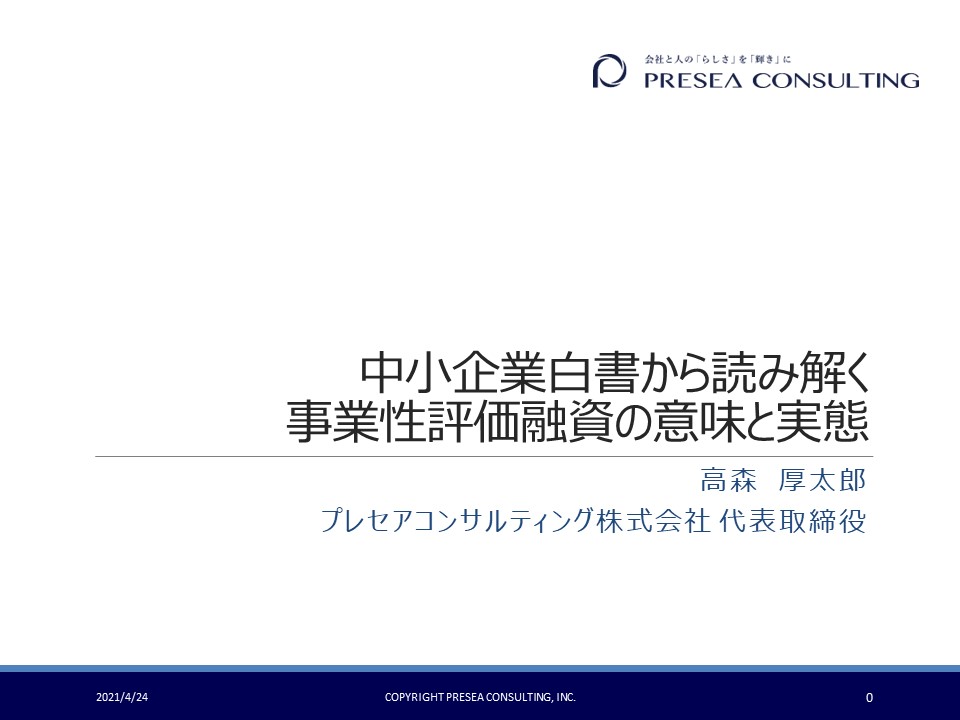
「中小企業白書から読み解く事業性評価融資の意味と実態」のパートでは、最新の中小企業白書の内容を踏まえて、事業性評価は飲食店のケースを用いたワークを行います。
独立コンサルタント、信金等の金融機関、あるいは公的な支援機関での各々の経験も交え、充実した意見交換の機会となりました。
ご参加の中小企業診断士の皆さまの今後のキャリア・活動のヒントになれば幸いです。

(参考)タスクール理論政策研修 講師ページ:高森厚太郎